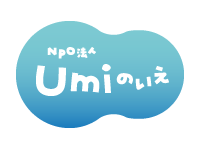こんにちは。スタッフ阿部亜美です。
今年で4回目を数える「おんぶシンポジウム」
たくさんの方に御来場頂き、ありがとうございました!
今回はシンポジストに、
だっことおんぶの研究所理事長 園田正世さん、
そして、アウトドア防災ガイド あんどうりすさんをお迎えしました。
冒頭は現役子育て中のお母さんふたりの
自身の子育てとおんぶについて、写真を交えたスピーチで始まりました。
ぴったりおんぶをすることで辛い時も幸せなときも
大切にこどもとの時間を過ごしてきたこと。
子育て中のママたちを勇気付けるお話でした。
そして、シンポジストお一人目の 園田正世さんのお話では、
高い位置でのおんぶが私たち日本人にとってどれだけ大切なのか、
歴史、各国の暮らしと文化と身体について、とても聞き応えのあるお話でした。
続いてあんどうりすさんのお話では、
災害時の母乳育児に関してのお話が、特に印象に残りました。
・被災しても母乳育児を継続できること
・母乳をわずかな量でも与えることができるだけで、
避難所で多くみられる感染症リスクを減らすことができること。
・母乳育児の人には母乳が継続できる支援をし、本当にミルクが必要な人にも、
災害が終わるまで継続してミルクを供給できる支援が必要なこと
・それまでの子育てを大切にする支援が重要であること
そしてあんどうりすさんが持ってきてくださった防災グッズ、アウトドアグッズを
実際に触らせていただき、より具体的に備えを感じることができました。
こどもが産まれて、
❝命にかえてでも守りたい。…でもこの子たちのためにも必ず生き延びるんだ❞
と思うようになりました。
いつ大地震、大災害がおきてもおかしくない昨今。
自分や家族を守るためにも物の備え、知識の備えが重要ですね。
それでは、「ふんわりすくすく赤ちゃん講座」の講師、加田洋子さんの
レポートをシェアさせていただきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「第4回おんぶシンポジウム」を開催いたしました。
テーマは、「いのちをつむぐおんぶ〜心と身体と防災」
シンポジストに
だっことおんぶの研究所理事長 園田正世さん
アウトドア防災ガイド あんどうりすさんをお迎えして、
赤ちゃんとお母さんたち、子育て支援者たちが参加して
おんぶのこと、防災のことを学びあいました。
Umiのいえスタッフ近藤なみの手遊びからスタート。
はじめての場所に落ち着かないお子さんも
「ひげじいさん」や「ぐーちょきぱーでなにつくろう」などの
楽しい歌に笑顔になりました。
司会進行は、Umiのいえ代表の齋藤麻紀子。
始まりの挨拶より。
「今、ここに子供といることを幸せに感じること、それが防災になるんですよ。
今日、防災のことを知ったら、自分の心に納めるのではなく
周りのお母さんに伝えてくださいね。みなさんでしっかり学んでいきましょう。」
続いては、おんぶで子育て中のおかあさん二人のスピーチです。
〇児玉 咲季さん「子育てとおんぶ」
待ち望んで来てくれた二人目の赤ちゃん。
でも子供二人の子育ては大変で他人と比べて、できない自分を責めて追い詰めた。
でも、幸せは求めることではなく、自分の中に持っていた。
「私にしかないもの、私にしかできないこと」があった。
悩んでいる時もおんぶは私の暮らしの中に溶け込んで、どんな時も寄り添ってくれた。
下の子をおんぶして上の子を抱っこして、身動きがとれない、でもそれが 安心だった。
〇安道 茜さん「息子の人生を背負い、肚がすわった」
食物アレルギーのある息子は成長もゆっくりさん。
乗り越えなくてはいけないことが沢山あったけれど、
ベビーウェアリング(布で子供を纏うように抱っこするおんぶすること)はいつも、
自分を支えてくれた。
歩き始めもゆっくりだったので、おんぶの時期も長かった。
でも、その時間は親子で気持を共有する時間だった。
日々、おんぶをして、大地を踏みしめ、私は母になっていったのだと思う。
そしてシンポジストお一人目の登壇は、この方です。
〇園田 正世さん
(だっことおんぶの研究所理事長)
「日本人の身体と子育て、文化」
沢山の貴重なスライドとともに、お話をしてくださいました。
・日本人と欧米人は骨格が違い、また身体の使い方も違い、また文化、環境も違う。
なので、欧米から入ってきた抱っこ紐をそのまま使いこなすことは難しい。
そのことを理解して、道具を使わなくてはいけない。
・日本のおんぶの歴史は長い。1980年代後半から抱っこが主流となるが、
それまで日本人はおんぶをして子を育てていた。
おんぶは日本人の身体と生活環境に適していた。
・おんぶされている子供は
日常生活を背中から見て理解する(共同注意)。
それは学校で学ぶ勉強とは異なる。社会を見ること、社会状況を知ることである。
布で高い位置に背負うおんぶは日本人の暮らしと身体に適したものだからこそ、
受け継がれてきたもの。
災害時は日々の便利さが奪われてしまう、でもそれは少し前の暮らしに戻ること。
その時に、昔からされてきたおんぶのスキルは、きっと親子を支えてくれます。
お二人目の登壇はこの方。
〇あんどう りすさん
(アウトドア防災ガイド)
「小さないのちを守るママの防災」
沢山の知恵と工夫を余すことなく伝えてくださいました。
・アウトドアのテクニックを防災に生かす具体的な方法
・防災のために入れておいた方が良い携帯アプリ
・クライミングの技を使ったしがみつき方
・古武術の技を使って怪我人の助け方
・家の中の安全対策グッズ
・今、ここで地震が起きたら、何をするのか?
などなど。
ママたちは一生懸命メモをしたり、うなずいたり。
全部は覚えきれないけれど、でも、大切なことはきっと心に強く残ったと思います。
持ってきてくださった沢山のアウトドアグッズや防災グッズを皆さん手に取って、
確認をしていました。早速、ご家庭で揃えた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
午前の最後は
〇兵児帯、晒など布をつかったおんぶの体験会
初めてさんも既に使っている方も
ベビーウェアリングコンシェルジュのアドバイスで楽に背負えて、お子さんもママも皆、笑顔でした。
体験していただいた皆様、ありがとうございました。
午後の時間は、子育て支援者が集まり、午前中のお話を振り返りながら、
「支援者が災害時、その場にいるお母さんたちに何が出来るのか?」
園田さんとあんどうさんのより具体的なお話を聞き、
そして、それぞれの現場で感じていることをシェアし意見交換をしました。
講師のお二人は
「普段の生活で工夫ができていないと災害時に何もできない。
災害時は普段よりもひどくなるのだから。
普段の生活で使いこなしているものこそが役に立つ。」
と繰り返し、お話されました。
便利なものに頼るだけでなく、日々の暮らしに知恵と工夫とすることで
いざという時に生き抜く力がきっと身につきます。
是非、親子で生き抜く力を育んでいきましょう!









(以上、撮影 加田務さん)


今回も「おんぶシンポジウム」を無事に開催することができました。
登壇してくださった方々、お手伝いをしてくださった方々、ご参加くださった皆様
お力添えをいただいた皆様に心より感謝申し上げます。
スタッフ英子